社会人を招いての合同授業の報告
7/4に(株)ユニオントラストの山口昌利氏を招いて「仕事をするということ」を切り口に講演をして頂いた。今回は2回目の講演で金澤、福井、山田そして辻ゼミの4ゼミナールの参加となった。前回は5/21に福井ゼミと辻ゼミの合同で基本的で一般的な仕事の話で「仕事の基本」の講演であったが、今回は少し踏み込んだ形となった。
山口氏は長く、サントリーにお勤めであったので、そこでの経験談もふまえ、第2回を「マーケティングの基本」とされ、営業に何が必要かということも述べられた。前回受講した学生から営業などの採用基準は何かと聞かれていたが、それに対しては、営業系・スタッフ系の採用においては、「ポテンシャル=思考力・実行力」と「人間性=一緒に働きたいか」がポイントになると回答されていた。また絶対に持っている方がよい資格については、営業系では「特に何か資格を持っていること自体が有利になることは無いと思います。資格を取るために勉強した・努力したというプロセスは、ゼミやサークル活動のいわゆる「ガクチカ」と同様にアピールすれば良いと思います」とおっしゃっていた。
また、山口氏が「学生のみなさんは、「行動を起こす」「一歩踏み出す」ことに躊躇いや不安があるようですね。「失敗にすることの恐れ」でしょうか? 成功も失敗も体験がまだまだ少ないとは思いますが、今まであまり大きなチャレンジはせずに、無難に身の丈に合った過ごし方をしてきている、ということでしょうか?」と逆に質問をされていた。
さらに「サントリーには「やってみなはれ」という企業文化の根幹を成している言葉があります。いわゆる「チャレンジの推奨」ですが、長年サントリーで働いてわかったことは、「やってみなはれ」には失敗がつきものということ。そして、「失敗の推奨」こそが、会社の成長の源泉であるということとお教え下さいました。
また、「いくつかの企業のサイトを調べてみると、「チャレンジの推奨」をしている企業は非常に多く、従業員のチャレンジを支援する仕組みを持っているところも多いようですね」と続けられ、7月2日の講義では、「挑戦」「チャレンジ」を取り上げた話をされました。
なお、サントリーの「やってみなはれ」は、ビール事業への参入を決めた際に初代社長が発した言葉で、ビール事業の歴史=やってみなはれの歴史そのものなので、自身が経験してきたビール事業の挑戦を題材に話を組み立てておられました。
学生たちにとっては、少し遠い会社の話になったと思います。3年次生の今だからこそ、こういう話を聞くことも大事なのではないかと思っております。
-

講演風景1
-

講演風景2
-
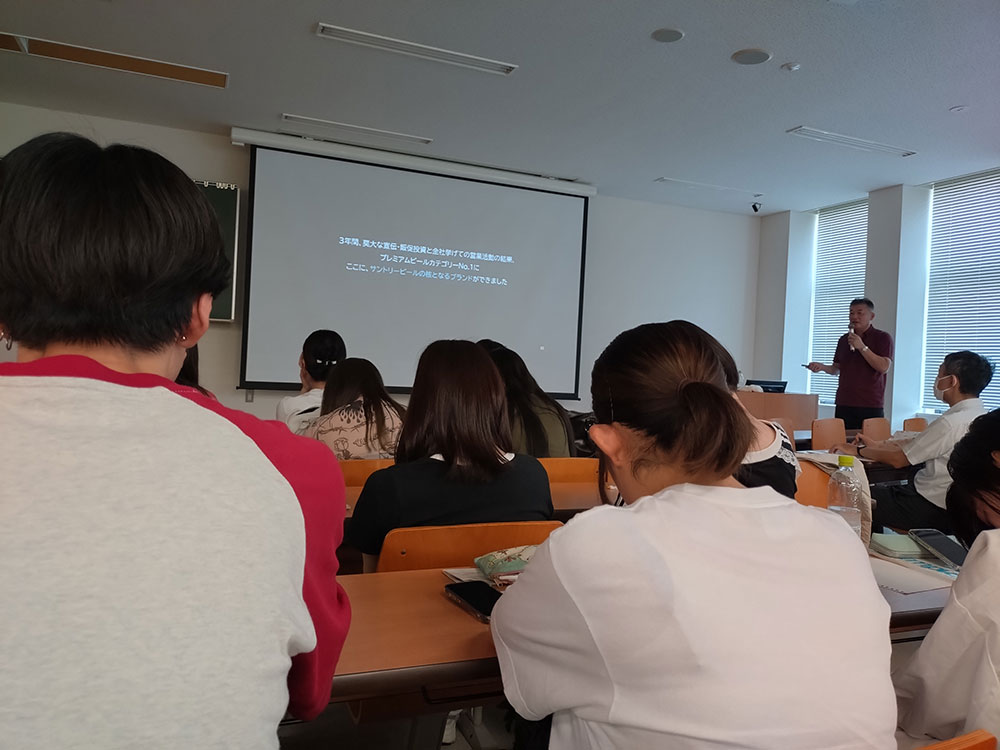
講演風景3